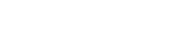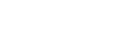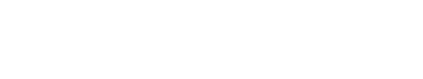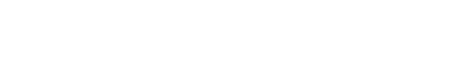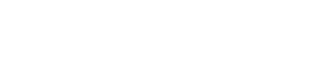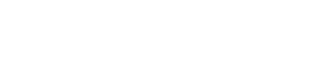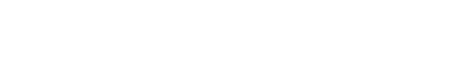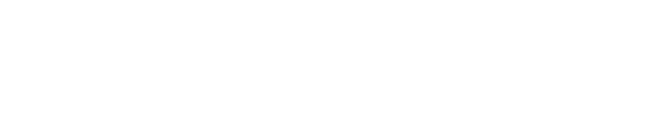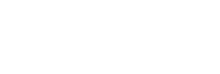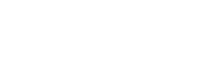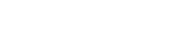- HOME
- ブログ
骨粗しょう症の症状と原因を医師が解説|早期発見のポイントとは?
2025.11.28

骨粗しょう症とは?
骨粗しょう症は、骨密度が低下し、骨がスカスカで折れやすい状態になる病気です。 国内には約1,280万人の患者さんがいるとされており、特に女性に多く見られます。男性が約300万人、女性が約980万人という推計データがあり、高齢化に伴って患者数は増加傾向にあります。 この病気の最も怖い点は、「痛みが出る頃には、すでに骨がかなり弱っている」ことです。自覚症状がほとんどないまま進行するため、気づかないうちに骨折リスクが高まっていることも少なくありません。 骨粗しょう症になると、日常のちょっとした動作で骨折しやすくなります。転倒だけでなく、重い荷物を持ち上げたり、くしゃみをしたりするだけで骨折することもあるのです。骨粗しょう症の主な症状
初期は自覚症状がほとんどない
骨粗しょう症の初期段階では、痛みなどの自覚症状がほとんどありません。 これが早期発見を難しくしている大きな理由です。骨がもろくなっているだけでは痛みは発生せず、骨折が起きて初めて症状が現れることが多いのです。 特に50歳以降、または閉経後の女性は、骨密度検査を受けることが必須です。閉経後10年ほどで骨量が急激に減少することが知られており、この時期の検査が将来の骨折予防につながります。軽度の症状
骨粗しょう症が進行すると、以下のような症状が現れることがあります。- 背中が丸くなってきた気がする
- 身長が以前より縮んだ
- 時々腰や背中が痛む
- 立ち上がる時に腰が痛む
- 重いものを持つと腰が痛む
重度の症状
骨粗しょう症が重度になると、次のような明らかな症状が現れます。- 明らかな猫背
- 大幅な身長低下(若い頃より2cm以上低下)
- 強い背中・腰の痛み
- 転倒で骨折
骨粗しょう症の原因
加齢による骨密度の減少
 骨量は男女ともに20歳頃をピークに、年齢が進むにつれて減少していきます。
特に女性は閉経を迎える50歳頃から骨密度の減少が加速します。これは、腸管でのカルシウムの吸収が低下するため、カルシウムの吸収を助けるビタミンの働きが弱くなるため、そして女性ホルモン(骨吸収の働きを弱める作用がある)の分泌が低下するためです。
女性は更年期以降、特に骨密度の低下が進みやすく、骨粗しょう症になるリスクが高くなります。閉経後の女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、骨の形成を促進する作用が弱まることが主な原因です。
骨量は男女ともに20歳頃をピークに、年齢が進むにつれて減少していきます。
特に女性は閉経を迎える50歳頃から骨密度の減少が加速します。これは、腸管でのカルシウムの吸収が低下するため、カルシウムの吸収を助けるビタミンの働きが弱くなるため、そして女性ホルモン(骨吸収の働きを弱める作用がある)の分泌が低下するためです。
女性は更年期以降、特に骨密度の低下が進みやすく、骨粗しょう症になるリスクが高くなります。閉経後の女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、骨の形成を促進する作用が弱まることが主な原因です。
栄養バランスの偏りと運動不足
骨を形成するためには、カルシウムやビタミンDなどの栄養素が必要です。 偏った食生活や運動不足は、骨形成に必要な栄養素の不足や骨の刺激不足を引き起こすため、骨密度の低下につながります。特に過度なダイエットや偏食は、若い世代でも骨粗しょう症のリスクを高めます。 運動量の低下による骨への刺激が減ることも、骨密度低下の一因です。骨は刺激を受けることで強くなるため、適度な運動習慣が骨の健康維持に欠かせません。喫煙と過剰な飲酒
タバコに含まれるニコチンやアルコールは、骨形成細胞の働きを妨げるため、骨密度の低下につながります。 喫煙習慣や過度の飲酒がある方は、骨粗しょう症のリスクが高まります。これらの生活習慣を見直すことが、骨の健康を守る第一歩です。その他のリスク要因
以下のような特徴がある方は、骨粗しょう症になりやすいと言われています。- 家族歴がある(母親や祖母の背中が曲がっていた、骨折の既往歴がある)
- やせ型である(BMIが低い)
- 身長が高い
- 平均より早い45歳頃までに閉経を迎えた
早期発見のための検査方法
骨密度検査(DXA法)
当院では、DXA法(全身型骨密度測定装置)による腰椎・大腿骨の骨密度測定を行っています。 これは2種類のX線を用いて骨量を測定する方法で、他の測定法と比べて精度が高いのが特徴です。背中や足の付け根の骨などに2種類のX線を当てて骨量を測ることで、正確な骨の状態を把握できます。 4か月に1回の検査を推奨しており、定期的なチェックで骨密度の変化を継続的に管理します。骨密度が80%未満の場合は半年ごとに検査を実施し、80%以上に改善した場合は年1回に頻度を戻して経過観察を行います。骨代謝マーカー
血液検査で「骨を壊すスピード・作るスピード」のバランスを評価します。 骨代謝マーカーは、骨を壊すスピードと作るスピードのバランスを数値化するもので、異常値は骨折リスクの指標になります。この検査により、現在の骨の状態だけでなく、将来の骨折リスクも予測できます。X線検査
胸椎・腰椎の骨折・変形の有無を確認します。 背骨の圧迫骨折は痛みが軽いもしくは痛みがないため、骨折に気づかない患者さんもいます。X線検査で早期に発見することで、適切な治療につなげることができます。早期発見のセルフチェック
ご自身やご家族で以下のチェックを試してみてください。- 壁にからだをくっつけて立ってみて後頭部がつかない
- 身長を測定して若いころより2cm以上低下している
神保町整形外科での治療方法
食事療法
丈夫な骨の材料となる栄養素をしっかり摂取することが基本です。- カルシウム(乳製品・小魚など)
- タンパク質(肉・魚・卵)
- ビタミンD(魚・きのこ類)
- ビタミンK(野菜)
運動療法
 軽い負荷をかけることで骨が強くなり、筋肉がつくことで転倒予防にもつながります。
ウォーキングなどの無理なく続けられる運動を提案します。運動によって骨は刺激されて強くなり、また筋肉も鍛えられて骨折の原因となる転倒防止につながります。
日常的に体を動かす習慣をつけることで、ロコモティブシンドロームやメタボリックシンドロームなどの予防効果も期待できます。
軽い負荷をかけることで骨が強くなり、筋肉がつくことで転倒予防にもつながります。
ウォーキングなどの無理なく続けられる運動を提案します。運動によって骨は刺激されて強くなり、また筋肉も鍛えられて骨折の原因となる転倒防止につながります。
日常的に体を動かす習慣をつけることで、ロコモティブシンドロームやメタボリックシンドロームなどの予防効果も期待できます。
薬物療法
症状に応じて以下の薬剤を組み合わせ、「骨を壊すスピードを抑え、作る力を高める」治療を行います。- 活性型ビタミンD3製剤(カルシウムの吸収を助ける)
- SERM(骨を壊れにくくする)
- ビスフォスフォネート(骨を壊れにくくする)
- 抗RANKL抗体(骨を壊れにくくする)
- 副甲状腺ホルモン製剤(骨を作る力を高める)
- 抗スクレロスチン抗体(骨を作る力を高める)
治療後のアフターフォロー
骨粗しょう症は「一度よくなったら終わり」ではなく、長く付き合いながら守っていく病気です。 骨密度80%未満の場合は検査を半年ごとに実施し、80%以上に改善した場合は年1回に頻度を戻して経過観察を行います。治療歴を継続して管理することで、将来の骨折リスクを減らすことができます。 一度骨折すると、その後1年以内に再び骨折しやすくなるため、継続的なフォローが非常に重要です。こんな方は早めの検査をおすすめします
以下のような症状や心当たりがある方は、早めの検査をおすすめします。- 背中が丸くなってきた
- 身長が以前より低くなった
- 転んだだけで骨折した
- 腰・背中が時々痛む
- 運動量が減った
- 閉経した
- やせ型である
- 偏食・極端なダイエット
- 喫煙・飲酒習慣がある
著者情報
神保町整形外科 院長 板倉 剛
経歴
投稿者: